|
|
|
不可視なものが、立ち現れる
視えないものが見える。と言っても、怪し気な霊媒師の話ではない。誰もが経験したことのある、視えない
ものが見えるという話である。矛盾を孕んだこの事象を、さてこれから言葉で説明しようと思うものの、こ
れが難しい。だったら言葉にできない“ニュアンス”だけでも伝わればと言うことで、こんな喩えをする。
ここに2枚、モナリザのポストカードがある。1枚のカードにはモナリザの顔に逆「への字」の髭をチョンチ
ョンと描き込み、友人に送る。1週間後、何も書き加えていない残りの1枚をその友達に再送する。友人
は2度目に送られてきたポストカードを見て、どう思うだろう。「モナリザ、髭剃った?」友人はそう思うに違
いない。何度も目にしたモナリザの顔が、この時ばかりは髭を剃ったモナリザに見えてしまうのではない
か。視えない髭が、剃り落とした髭(不在)という在り方で顕現する。冒頭の命題「不可視なものが、立ち
現れる」とは、無いのに有る、そんな感じである。“ニュアンス”は伝わっただろうか。
同じものが全く違うものに見える場合もある。これも、視えないものが見える例と言えよう。例えば、毎日
使う通勤電車。いつものホームの向こう側にある、逆の方面行きのホームに立って、「もう今日はズル休
みだ!」と思いながらゆっくりとホームに入って来る電車を見た時、私はこう思う。
「いつもの黄色い電車とは全く違う、黄色い電車が来る!」
同じものなのに、その時の心境あるいは過去の記憶または新たに獲得した知恵によって、後者のそれ
が全く違って見えることって、アリマセンカ?
アルハズデス。こんな経験は日常にあふれている。しかし悲しい哉われわれは、ひと瞬き、ふた瞬きする
あいだに、この貴重な違和感を否定し消し去ってしまうのです。髭を剃ったモナリザも、楽しげな黄色い
電車も、一瞬にして元のモナリザに、通勤電車と同じ黄色い電車に戻ってしまう。非合理を排除する理性
という奴が、そう判断するのです。錯覚、思い違い、迷い、そんな言葉を使って「不可視なものが、立ち現
れる」ことなどあるはずないと、冷笑まじりに騙るのです。
ダケドミナサン、理性ナンカニダマサレテハイケナイ。この違和感によって見ることのできる不可視なもの
こそ、世界を「世界」と呼び、私を「私」と呼び、すべてのものをそれぞれ「何々」と呼ぶことのできる、言葉
の「意味」なのだ。物質としては存在しないが、「意味」は確かに存在する。私たちの中に。
ここから話は前回の続き、テラのオープンシアター(毎月1回、新宿にて開催)の「感想」につながる。前
回は「声から語り、語りから声(動き)」を仕掛けに、身体を「開き」全体を「引き受ける」実験的な試み(即
興エチュード)について感想を述べた。今回は、前回言及することができなかった「起つ」について、あれ
これ考えてみた。
「開き」「引き受ける」身体があって、その先に「起つ」身体がある。確かにそうなのだが、「起つ」その主語
は身体(役者)ではない。精確に言うと、身体が「起つ」のではなく、起つものは「意味」なのである。意味
が「起つ」。物質としては存在しない、不可視な意味。それでいて、疑いようのない、私たちの中に確実に
存在する意味。その意味が「起つ」とは、どういうことか?
老女を見て、年老いた女性がいるなと思うだけでは、意味が「起つ」とは言えない。年老いた女性がいる
と認識しながらも、物理的には視えない「老女」が立ち現れた時、意味が「起つ」と呼べるのだ。初めから
存在しているものを「ある」と認識しても、意味は「起たない」。ないものがある。モナリザの髭のように、不
在という仕方で顕現する。トテモ、ワカリズライネ。ここは理論的に考えてはダメ。ニュアンス。ないものが
ある、一瞬の違和感、ソレヲダイジニシテ。理性ナンカニダマサレテハダメ。
もう一度言う。身体(私)が意味を起たせるのではない。意味が起つ、意味が生起するのだ。身体(私)に
はどうすることもできない。モナリザの髭は、視ようとして見るものではない。どうしようもなく見えてしまう
のだ。それが意味なのだ。何度でも言う。私が何をしようと関係なく、意味が「起つ」のである。「起つ」の
は意味である。
舞台のダイナミズム、観客の興奮が最高潮に達するのは「不可視なものが、立ち現れた」その瞬間なの
ではないか。演者の迫力、舞台の構成力あってのことだが、真の観客が興奮するのは視えないものが、
不在であるものが、実際に見え、聞こえ、感じることができるからだろう。
|
|
|
|
|
|
「感想」を書いてみました。
リラックスしながら集中力を高めていく。声や周りの動きをあるがままに受け取り、余計な意図を混ぜず
に反応する。自然体。身体は場となり、媒介(メディア)となり、言葉となる。舞台に立つ身体とは、まずは
「開き」すべてを「引き受け」そして「起つ」ことなのだろう。
テラWSの作業では、身体を「開く」ために、具体的な仕掛けを用意する。8月31日のWSのテーマは「声か
ら言葉へ、語りから声(動き)へ」。無形から有形へ、さらに有形(意味の発生)から無形(無意味化)へ、
変容する身体を捉えるための具体的な仕掛けが用意された。
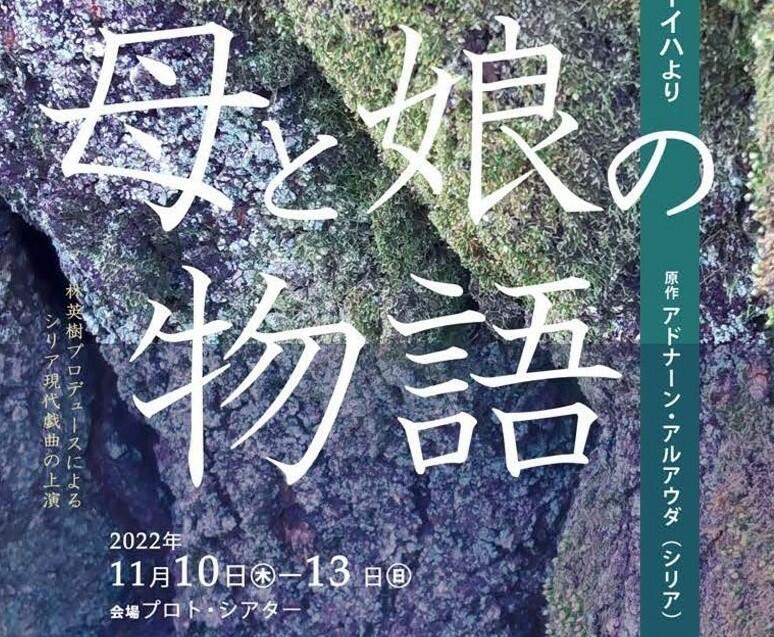
まずは、言葉以前の意味をもたない波動のような声(ときに沈黙)を発する者が指名される。そして、もう
1人。その声を手掛かりに、即興的に言葉を吐き出す者が指名される。そして2人によるエチュードがは
じまる。互いに相手の音声、言葉、動きに意識を集中させる。あるがままに反応することで、両者の自意
識は薄れ、何者かにつき動かされるかのように、徐々に、ある時は加速度的に両者の意識は変容して
いく。声を発する者は、語り手の言葉(意味)を再び声へ還元(無意味化)することで、身体の位相はさら
に深化する。一方、語り手は、考えながら話すといった主体的な語りが難しくなり、次第に「言葉」そのも
のが主導権を握るようになる。私でなく「言葉」が、言葉そのものが言葉を話しているかのように。行き先
を失ったとしか思えない「言葉」の連なりが、私から離れて揺曳する。深化する声と表層を漂う言葉。そこ
にあるふたつの身体は共振しながら、声(無形)言葉(有形)と化す。
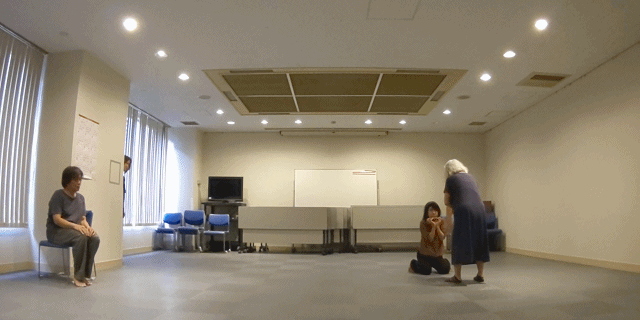
今回のWSでは、声と言葉(語り)を仕掛けとしたが、身体を「開く」ための仕掛けは多様にあり、これまで
のWSでもいくつも試みられてきた。時間、記憶、物語、童話、イメージ、概念、空間構成などなど。これら
を切り口に、身体の現象(無形から有形、有形から無形へ)を自覚する作業を繰り返してきた。
これらの作業の先にあるものとは何か?
それは「起つ」ことである。蜂起、勃起、縁起、決起、奮起、想起、躍起、突起、起立、‥兎に角なんでも
いいから「起つ」ことなのだ。テラのWSの作業を見れば分かることだが、「起つ」その主体は、私という一
人称でないことは明らかである。では誰? それは次回まで、しばらく考えてみたいと思います。
|
|
|
|
|
|
前回の「感想」で、このような意見を述べた。
私が何をしようと関係なく、意味が「起つ」のである、と。初めから存在しているものを「ある」と認識して
も、意味は「起たない」とも。
これに対する疑問として、そもそもこの文脈で使われている「意味」の意味が分からない。意味は、ふつう
に言葉の意味のことではないの?または、ここでは意志を持つ人のように擬人的に「意味」という言葉を
使っているが、そもそも「意味」が主体になり得るの?
それともう一つ。これは役者が想う疑問となるのだろう。舞台に立つ身体として「開き」「引き受け」そして
「起つ」と述べていたが、「起つ」その主体が意味であるなら、身体(私)に何ができるの?何をすべきな
の?
こうした疑問に答えるべく、意味とは?身体(私)と意味との関係は?身体(私)にできることとは?などに
ついて考えてみたい。
一般的な「意味」を構造的に表現するなら、翻訳がわかりやすい。知らない外国語に対して、その日本語
が意味となる。つまり辞書的に〇〇の意味は〇〇であると。古典を現代語訳する場合も同じだろう。流
行りのJK語を言い当てる陳腐なクイズも、問われるのは意味だ。意味するもの(シニフィアン)があって、
それに対応する概念(シニフィエ)がある。
このように「〇〇の意味は?」と言ったら、一般的には言葉の意味を求めていると理解するだろう。では、
この〇〇に「人生」という言葉を入れてみよう。
「人生の意味は?」
そう聞かれて、「人生」とは、人が生まれてから死ぬまでの…、と辞書的に答える人はいないだろう。即答
出来る人も少ないだろう。なぜ?おそらく聞かれた人は(あなたにとって)を質問の前に付けているからで
はないか。人生の意味は人それぞれ違うってことを知っているからだ。シニフィアンとシニフィエは、必ず
しも一対一にはならない。
「人生」だけではない。家族でも会社でも学校でもいい。身の回りにある親しみのあるもの、逆に苦手なも
の。それらの意味は私によって定義される。同じ家族でも「家族の意味」はひとつではない。また、意味
は固定されることなく、時とともに変化する。
次は、「意味」は主体になり得るの?という問いである。主体、主語、主人、主宰、主従などの「主」には、
ぬし、あるじ、中心となるもの、支配する人、つかさどる人(統率する人)のほか、「神霊の宿る所」(神霊
の代わりとして祭るもの)という意味がある。それに倣えば「意味が主体になる」とは、意味があるじとなっ
て中心に座し、全体を支配するとともに、意味が神霊の宿る場所となる。
「主」の用法のポイントは、支配と神霊。主体を支配関係で言い表すと、当然支配する側が主体となるだ
ろう。前の段落で、ものの意味は人それぞれに違いがあり、固定化せず時とともに変わりゆく、と述べ
た。人により意味する内容が変わるというわけだ。であれば、支配関係はやはり人が主体で、意味は被
支配となる。そう考えるのが一般的だ。であるが、はたしてそうだろうか。人は意味を支配しているのか。
疑問である。
結論から言うと、人は意味に支配されている。もう一度、「家族の意味」を考えてみよう。三人姉妹でも、
人形の家でも、ギリシャ悲劇でも現代劇でも何でもよい。登場人物それぞれが抱く「家族像」(家族の意
味)を思い出してほしい。彼ら彼女らは個別に違う「家族の意味」をもっているが、主体的というよりも逆
に、自分の置かれた状況から非主体的に、被支配的に家族像を持たされている。つまり、意味に支配さ
れているのだ。そして劇の進行とともに、それが徐々に変化し、不可視であるはずの「意味」が見え(ここ
は「意味」が起つ、と言い換えたい)、観客は感動する。
芝居の話になってしまったが、日常も同じ。家族に限らず、社会、国家、民族、宗教…、みな自分の置か
れた状況から非主体的に「〇〇観」を持たされ、その中で足掻いている。
最後の問い。舞台上で「意味」が起つために、役者は何をすれば良いの?
何もしなくていい。それが答え。余計なことはするな。それも答え。禅宗ではないが、唯「開き」唯「受け入
れる」身体ニナルヨウ精進スベキ、それしか言えない。私モ、ワカラナイ、ノヨ。タダ、理性ニハ、ダマサレ
ルナ。
|
|
|
|